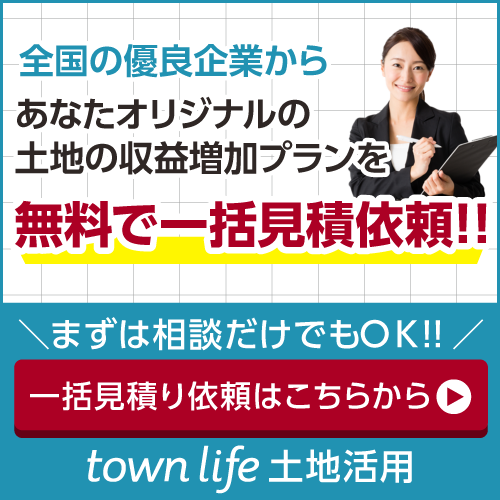マンションの減価償却の全貌とは?計算方法も解説!
- 更新日:2025.01.29

マンション投資においては、減価償却を正しく理解することで節税効果やキャッシュフローの改善が期待できます。
本記事では、減価償却の基本から計算方法、リフォーム費用の扱いなど、マンション投資に必要な知識を網羅的に解説します。
本記事でわかること
- 減価償却の基本的な仕組み
- マンションの減価償却の対象と法定耐用年数
- マンションの減価償却費の計算方法
- マンションの減価償却のメリット
マンション経営に関して最適なプランを知りたい場合はタウンライフ土地活用の利用がおすすめ。
たった3分の情報入力で、あなたに最適な活用プランを複数の優良企業から一括無料で手に入れることができます。
緑ボタンからタウンライフで
土地活用プランを一括比較!

POINT

あなたにぴったりの土地活用プランを無料で手に入れよう!

全国130社以上の優良企業に一括で依頼が可能!

依頼はオンラインでかんたん3分!
無料一括比較してみる
減価償却とは何か

まずは、減価償却の基本と耐用年数の概念、またマンションにおける重要性について整理してみましょう。
減価償却とは、建物などの資産が時間とともに価値が減少していく分を、会計上あるいは税務上の経費として計上する仕組みです。
※各項目をタップすると詳細にジャンプします。
減価償却の基本的な仕組み
減価償却は、建物が日々劣化し価値が下がっていく分を毎年の経費として認識する会計上の処理です。
マンションを取得した場合、購入時から耐用年数が終わるまで建物の取得価額を分割し、毎年一定額もしくは一定率を経費に算入します。
これにより、実際の所得を圧縮して税負担を軽減しつつ、投資全体の収支バランスを整えることが可能です。
なお、減価償却は強制償却とされるケースが多く、計上を怠ると税務上の問題にもつながるため、正確な算出が重要になります。
減価償却と耐用年数の関係
減価償却を行ううえで重要になるのが、法定耐用年数です。
これは国が定めた基準で、建物の構造や用途によって年数が異なります。
例えば、鉄筋コンクリート造のマンションであれば47年が一般的な耐用年数となり、その期間にわたって取得価額を分割します。
耐用年数に基づく償却率を用いることで、毎年の減価償却費を正しく計上でき、税務申告の裏付けにもなります。
マンションの減価償却が重要な理由
マンションの減価償却が注目されるのは、節税効果とキャッシュフローへの影響が大きいからです。
減価償却費を経費として計上することで課税所得を下げられ、結果的に手元に残るお金を増やすことができます。
また、毎年計画的に償却を行うことで、将来の大きな税負担を平準化し、投資リスクを分散できるメリットもあります。
こうした税務上のメリットを最大限活用するためには、正確な計算と適切な申告が欠かせません。
マンションの減価償却の対象と法定耐用年数

減価償却できる資産の範囲と、マンションに適用される法定耐用年数について把握することは大切です。
投資家としては、耐用年数を正しく理解し、減価償却のタイミングや金額を計画的に把握して、マンション経営の長期戦略を設計することが求められます。
※各項目をタップすると詳細にジャンプします。
減価償却の対象となるもの
マンションにおいて減価償却の対象となるのは、土地を除いた建物部分と、その建物に付帯する設備です。
例えばエアコンや給排水設備などは、その設備ごとに耐用年数や償却率が設定されており、建物本体とは別に償却する場合があります。
これらを正しく仕訳することで、正確な経費計上を行い、将来の税負担を適切にコントロールすることが可能になります。
マンションの構造別の法定耐用年数
マンションの最も一般的な構造である鉄筋コンクリート(RC)造や鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造では、法定耐用年数として47年が設定されています。
これに対して、鉄骨造や木造の場合はより短い耐用年数が割り当てられるため、同じ不動産投資でも構造次第で経費計上の時期や金額が変わってきます。
法定耐用年数は税務当局が決めた基準であり、実際の建物寿命とは切り離して計算する点がポイントです。
付帯設備の法定耐用年数
マンションに備え付けられているエレベーターや消防設備、給排水設備などは、それぞれ個別に定められた法定耐用年数に基づいて減価償却を行います。
一般的に付帯設備の耐用年数は建物本体よりも短めに設定されることが多く、設備の更新時期や修繕のタイミングと減価償却のスケジュールをどのように連動させるかが投資戦略上のポイントになります。
設備ごとの年数を把握し、計画的にメンテナンスを行うことで、資産価値の維持と税務上のメリットを両立しやすくなります。
緑ボタンからタウンライフで
土地活用プランを一括比較!

POINT

あなたにぴったりの土地活用プランを無料で手に入れよう!

全国130社以上の優良企業に一括で依頼が可能!

依頼はオンラインでかんたん3分!
無料一括比較してみる
マンションの減価償却費の計算方法とは

マンションの減価償却費の計算方法について説明します。
減価償却は、資産(この場合はマンション)の購入費用をその資産の使用期間中に分割して経費として計上する方法です。基本的な手順は以下の通りです。
※各項目をタップすると詳細にジャンプします。
資産の取得価額を把握する
まず、マンションの購入費用(取得価額)を確認します。
これには物件そのものの価格だけでなく、取得にかかった費用(登録免許税、不動産取得税、仲介手数料など)も含まれます。
減価償却方法を選択する
日本では通常、「定額法」または「定率法」のどちらかを選びます。
定額法:毎年同じ金額を減価償却する方法。
定率法:毎年残存価額の一定割合ずつを減価償却する方法。
ただし、一般的に不動産(建物)は定額法が使用されることが多いです。
| 指標 | 定額法 | 定率法 |
| 計算の安定性 |
|
|
| 初期費用の大きさ |
|
|
| 経費計上 |
|
|
| 主な利用場面 |
|
|
耐用年数を決定する
建物の種類によって法定耐用年数が異なります。
例えば、鉄骨鉄筋コンクリートまたは鉄筋コンクリート造りの住宅用の建物なら、耐用年数は47年とされています。
他の構造の場合は異なる耐用年数が適用されることがありますので、具体的には国税庁の耐用年数表を参照してください。
減価償却費を計算する
定額法を例に説明します。
(年間減価償却費)=(取得価額)÷(耐用年数)
例えば
取得価額が5,000万円
耐用年数が47年
の場合、
この場合の年間減価償却費は、
50,000,000円÷47年=1,063,830円
となります。
初年度の月割計算(該当する場合)
資産を取得したのが年度の途中である場合には、初年度のみ月割計算を行います。
例えば、取得したのが7月であれば、その年度の減価償却費は年間減価償却費の6/12(7月から12月までの6ヶ月分)になります。
<その他の考慮点>
残存価額:日本の税法では、建物の残存価額は通常ゼロとされます。
改修・修繕費:大規模な改修費用は資産価値を増やすものと見なされ、別途減価償却の対象となることがあります。
不動産の減価償却に関しては、税理士や専門家に相談して具体的な計算を確定することをお勧めします。
リフォームやリノベーションでの減価償却

取得後に行うリフォームやリノベーション費用の扱いも減価償却計算に影響します。
マンションを購入した後、付加価値を高めるためにリフォームやリノベーションを実施することは珍しくありません。
これらの工事費用が修繕費として一括経費にできるのか、あるいは建物の価値を増加させる資本的支出として減価償却の対象となるのかを正しく判定することが大切です。
※各項目をタップすると詳細にジャンプします。
リフォーム費用の減価償却
リフォーム工事では、キッチンや浴室などの設備を交換したり、外壁や共用部分などを改修したりするケースがあります。
これらが原状回復を超える大規模改修に該当する場合、建物価値の向上とみなされるため、資本的支出として減価償却の対象になることが多いです。
一方で、軽微な修繕や現状回復程度の工事なら、修繕費として一括経費計上できる可能性があります。
どちらに該当するかは工事内容を精査して判断し、税務リスクの回避に努めましょう。
リノベーション費用の計上方法
リノベーションは間取り変更や性能向上を目的とした大規模工事が多く、建物の使用価値や耐用年数を延ばすことが意図されます。
そのため、一般的には資本的支出として扱われ、減価償却による経費配分が必要です。
一度の出費で一気に経費計上できない分、長期的な視点で見るとマンションの品質向上と価値維持に寄与し、将来的な賃料アップや資産売却時の優位性につながる可能性があります。
修繕費と資本的支出の違い
修繕費とは経年劣化や故障を直して現状に復するための費用であり、通常は一度に経費として処理できます。
一方、資本的支出は建物の原状を超えた性能向上や価値増加をもたらすもので、減価償却の対象となります。
両者を正しく判定するためには、工事内容や目的を一つひとつ確認し、領収書や工事報告書と照らし合わせることが必要です。
誤った処理を行うと、後に税務当局から修正を求められるリスクがある点にも注意が必要です。
マンション経営における減価償却のメリットと注意点
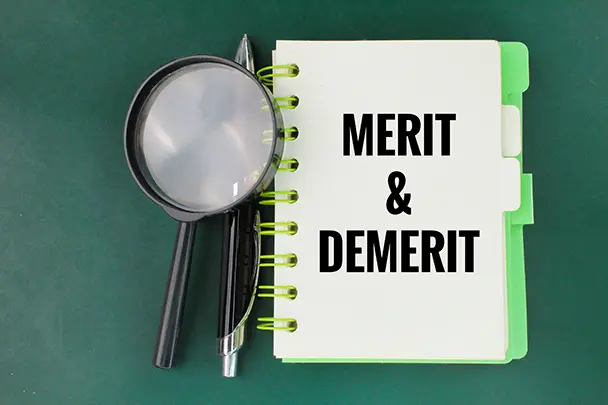
減価償却の効果を最大化し、税務リスクを回避するために理解しておきたいポイントをまとめます。
マンション経営において減価償却を正しく活用すれば、課税所得を下げることで節税効果が得られるだけでなく、物件の収支計画を計画的に進めやすくなります。
※各項目をタップすると詳細にジャンプします。
節税効果とキャッシュフローへの影響
減価償却費は実際の出費がないにもかかわらず損金として計上することができるため、課税所得を圧縮し、手元資金を厚くすることができます。
一方で、減価償却による帳簿上の価値減少は売却時の譲渡所得計算にも影響を及ぼすため、将来的に不動産を売却する場合の収支予測にも注意が必要です。
正確にキャッシュフローを把握し、投資効率を高めるためには、減価償却の仕組みをしっかり理解しておくことが不可欠です。
税務申告時における注意点
税務申告で誤った減価償却費を計上すると、後日税務当局から修正や追徴課税を求められるリスクがあります。
例えば、建物と土地の割合を誤って計上したり、減価償却を行わなかったりすると、不正確な損益が申告される可能性があるためです。
誤りを避けるためには、青色申告決算書や不動産収支内訳書などを正確に作成し、証拠書類をきちんと保管しておく必要があります。
確定申告で必要な書類と手続き
不動産収支内訳書や減価償却費計算明細書は、確定申告時のマストアイテムです。
青色申告を行う場合には、これらの書類に加えて複式簿記での帳簿管理が求められ、正確な所得計算により最大65万円の控除が得られる場合があります。
各書類には売買契約書や固定資産税通知書などの根拠資料がセットで必要になるため、購入から申告までの間にきちんと整理しておくことが大切です。
税務調査への備え
マンション投資を行うにあたり、税務調査の対象となった場合でも正しく対応できるよう、購入時の契約書や減価償却費の算定根拠を示す書類の保管が必須です。
特に、土地と建物の配分やリフォーム費用の内訳などは調査で確認されやすいポイントとなります。
日頃から証拠書類を整理・保存することで、万が一の税務調査にもスムーズに対応し、余計なトラブルや追加費用を回避することが可能です。
マンション投資戦略で考慮するポイント
減価償却は単なる経費計上だけでなく、資金繰りや物件の修繕計画といった運用面にも密接に関わります。
例えば、建物の残存耐用年数を意識してメンテナンスやリフォームのタイミングを図り、節税効果と資産価値の維持を同時に追求することが可能です。
マンション投資の成果を最大化するためには、収支計画と減価償却を一体で考え、長期的な視点でプランニングを行う必要があります。
減価償却と資産価値の維持
定期的な修繕や設備投資を行うことで、マンションの資産価値や入居者満足度を高めることができます。
こうした取り組みは減価償却と組み合わせることで、修繕費や資本的支出を計画的にコントロールでき、結果として投資の安定性や利回りを確保する上で大きな役割を果たします。
マンションのライフサイクルに合わせて適切な工事を実施し、長期的な資産価値を維持することが重要です。
リスク管理と投資計画
不動産投資には金利上昇や空室リスクなど、さまざまな要素が絡み合います。
減価償却の活用だけに注目するのではなく、キャッシュフローの変動や資産価値の下落リスク、さらに物件を売却するタイミングなども総合的に考慮し、投資計画を策定することが求められます。
リスクを十分に織り込んだうえで戦略を立てることで、マンション投資による安定した利益と将来的な出口戦略の両立が可能となるでしょう。
緑ボタンからタウンライフで
土地活用プランを一括比較!

POINT

あなたにぴったりの土地活用プランを無料で手に入れよう!

全国130社以上の優良企業に一括で依頼が可能!

依頼はオンラインでかんたん3分!
無料一括比較してみる
具体例で学ぶマンション減価償却
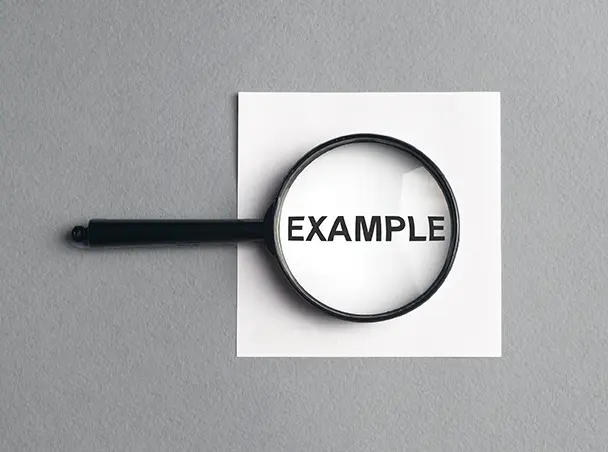
実践的な事例を通じて、新築・中古・賃貸物件における減価償却費試算の流れをつかみましょう。
減価償却を理解しやすくするためには、実際に数値を当てはめてシミュレーションを行うことが効果的です。
新築マンション、中古マンション、それぞれのケースで法定耐用年数をどのように設定し、毎年どの程度の経費を計上できるのかを具体的に把握することで、投資計画におけるキャッシュフローの見通しも一段と明確になります。
賃貸で運用する場合の家賃収入との兼ね合いも考慮し、リスクとリターンを見極めてみましょう。
※各項目をタップすると詳細にジャンプします。
新築マンションの計算例
たとえば都心部にある鉄筋コンクリート造の新築マンションを5,000万円で購入し、そのうち土地が2,000万円、建物が3,000万円とします。
47年の耐用年数を前提に、定額法で毎年約63万円程度を減価償却費として計上できる計算です。
購入初年度については取得月による按分が必要になる場合がありますが、おおよその目安を算出するだけでもキャッシュフロー管理に役立ちます。
中古マンションの計算例
築20年の中古マンション(RC造)を3,000万円で購入し、土地が1,000万円、建物が2,000万円とします。
既に法定耐用年数の一部を消化しているため、簡便法を用いて残存耐用年数を再計算し、仮に20年と設定した場合に定額法で毎年約100万円の減価償却費が計上できます。
築年数が経過している物件ほど耐用年数は短縮されるので、初期の経費は増えやすく、節税効果が出やすい傾向にあります。
賃貸物件の場合の計算例
賃貸用に運用するマンションで家賃収入が年間100万円あると仮定し、減価償却費が年間70万円の場合を考えてみます。
表面上は家賃で100万円の収入があるものの、経費として減価償却費70万円を計上できるため、課税所得は大きく圧縮されます。
実際にはローン返済や管理費などの支出もあるため、これらを含めたトータルのキャッシュフローを把握したうえで、長期的な収益性を見極めることが重要です。
まとめ:マンションの減価償却を理解して効果的に活用しよう
減価償却の仕組みを正しく把握し、マンション経営における長期的な戦略に取り入れることで、より安定した投資効果が期待できます。
マンションの減価償却は、投資効率を高めながら税務上のメリットを享受できる強力な手段です。
法定耐用年数や耐用年数超過時の計算方法、修繕費と資本的支出の区分など、正確な知識を身につけることが成功の鍵となります。
新築・中古を問わず、個々の物件の状況に応じて最適な償却計画や運用戦略を立案し、長期的に安定した収益を狙いましょう。
誤った計算や手続きを避けるために、専門家の意見を取り入れつつ、日頃から書類を整理して税務リスクを最小限に抑える管理体制を整えることが肝要です。
緑ボタンからタウンライフで
土地活用プランを一括比較!

POINT

あなたにぴったりの土地活用プランを無料で手に入れよう!

全国130社以上の優良企業に一括で依頼が可能!

依頼はオンラインでかんたん3分!
無料一括比較してみる