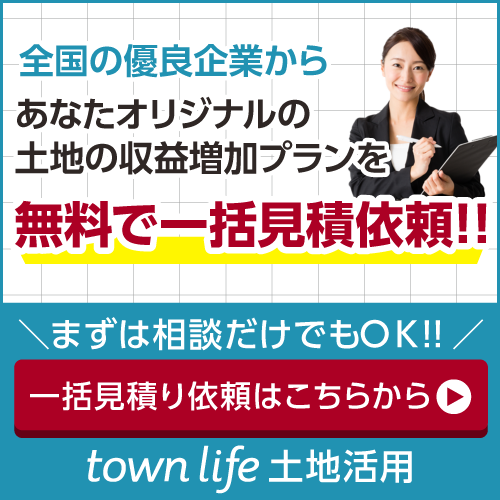実家の土地活用方法10選をご紹介!放置リスクや活用によるメリットまで徹底解説!
- 更新日:2025.05.01

本記事では、実家の土地を放置してしまうリスクや、実際に土地を活用するメリットを詳しく解説します。
さらに、豊富な活用方法や売却・寄付などの選択肢、相続税をはじめとする税金の基礎知識を押さえることで、より最適な土地活用を実現するための道筋を提供します。
ぜひ参考にしながら、自身の状況に合ったプランを見つけてください。
実家の土地活用方法
- アパート・マンション経営
- 戸建て賃貸経営
- 賃貸併用住宅の経営
- 駐車場・コインパーキング経営
- トランクルーム・倉庫経営
- 太陽光発電・ソーラー事業
- 資材置き場として貸し出す
- 高齢者向け施設・介護施設に活用
- 貸し店舗やテナントオフィス経営
- 借地として活用する
- 民泊・宿泊施設やキャンプ場への転用
実際にあなたが所有する農地に合った解決方法を知りたい方はタウンライフ土地活用の利用がおすすめ。
たった3分の情報入力で、あなたに最適な土地活用方法を複数の優良企業から一括無料で手に入れることができます。
緑ボタンからタウンライフで
土地活用プランを一括比較!

POINT

あなたにぴったりの土地活用プランを無料で手に入れよう!

全国130社以上の優良企業に一括で依頼が可能!

依頼はオンラインでかんたん3分!
無料一括比較してみる
実家の土地を放置するリスクとデメリット

相続後に実家の土地を放置していると、思わぬ負担やトラブルに巻き込まれる可能性があります。
放置している土地や建物は周囲の環境を悪化させるだけでなく、所有者自身にも思わぬ費用負担を生じさせるのが大きな問題です。
定期的に管理されていない空き家は、建物内外が荒れてしまい、景観の乱れや防犯面のリスクも高まります。
また、固定資産税などの税金は毎年課されるため、活用しないまま持ち続けているとコストが積み重なりかねません。
さらに、老朽化した建物は倒壊や火災の原因になることもあります。
万が一、周辺に被害が及べば損害賠償責任を負うリスクにもつながります。
建物のメンテナンス費用を抑えるために放置するのは逆効果であり、後々より大きな出費を招いてしまうケースも少なくありません。
自治体や近隣とのトラブルも軽視できないポイントです。
行政から空き家の除却や補修を求められたり、近隣住民とのあつれきが生じる場合もあります。
これらを防ぐためには、早めの対策と活用方法の検討が重要です。
※各項目をクリックすると詳細にジャンプします。
固定資産税・都市計画税が上がる可能性
空き家や無人の土地を長期間放置していると、固定資産税や都市計画税の優遇措置が適用されなくなる場合があります。
特に、建物が老朽化して安全性を欠く状態と判断されると、自治体から特例対象外に指定されることもあり、税金が増額するリスクが高まります。
優遇措置が外されると、維持費が跳ね上がり、毎年の納税額が大きな経済的負担となります。
対策としては、早めに建物を解体や修繕するか、別の用途で収益化を図ることが挙げられます。
さらに、土地活用を始めることで課税評価が変わり、結果として税金が安くなるケースも存在します。
賃貸や駐車場など何らかの活用方法を検討し、積極的に税負担を軽減できる仕組みを取り入れるのが賢明です。
老朽化による安全面の問題
建物が長年放置されると、壁や屋根、基礎部分の劣化が進みやすくなり、倒壊や火災のリスクが高まります。
特に木造住宅では、雨漏りやシロアリ被害によって構造がもろくなることが多く注意が必要です。
近隣住民に怪我や損害を与えた場合、損害賠償責任を追及される可能性もあります。
安全面への対応は、空き家を管理するうえで見逃せない要素の一つです。
日頃から点検や修繕を実施するだけでなく、いっそ建物を解体して更地にする選択肢もあります。
老朽化した住宅を放置してしまうと、維持管理コストより大きな損害やトラブルを招く恐れがある点を理解しておきましょう。
特定空き家に指定されるリスクと近隣トラブル
行政が定める「特定空き家」に指定されると、指導や勧告、場合によっては行政代執行による強制措置が取られる可能性があります。
特定空き家の指定は倒壊の危険や著しい景観の悪化などを基準に判断されます。
特定空き家に指定されると税制優遇の解除だけでなく、行政の措置費用を後から請求されることもあり、経済的負担はさらに増大します。
放置することで得られるメリットはほとんどなく、リスクが増える一方です。
また、近隣住民にとっても空き家は不安要素となり、コミュニティの安全や景観を損なう可能性があります。
こうしたトラブルを回避するには、早期の管理や利活用の検討が極めて重要といえるでしょう。
実家の土地活用を考えるメリット

実家の土地を放置せずに活用すると、さまざまなメリットが得られます。
土地活用を行うことで、まずは税金面での負担を軽減できる可能性があります。
賃貸経営などで不動産として評価が変わると、固定資産税や相続税が安くなるケースもあるため、経済的メリットは大きいといえます。
また、活用方法によっては収益を生み出し、親や家族の老後資金、日々の生活費を補填できるメリットもあります。
特に家賃収入や利用料収入などの安定的な利益は、資産を活かすうえで有望な選択肢です。
さらに、空き家や空き地のままにしていた場合に発生する近隣トラブルや治安面での不安を解消できるのも利点です。
地域の住環境を良好に保つことは、土地所有者にとっても重要な責任といえるでしょう。
※各項目をクリックすると詳細にジャンプします。
相続税や固定資産税の節税につながる
賃貸用のアパートやマンションを建てると、建物と土地の評価額が下がり、相続税や固定資産税の負担が軽減される場合があります。
これは小規模宅地の特例など、税制面の優遇措置を受けやすくなるからです。
さらに、更地よりも建物が建っているほうが課税標準が低くなることが多く、実質的な節税が期待できます。
固定資産税の優遇制度を上手に利用することで、長期的に見た維持コストを削減できる可能性があります。
こうした制度が適用されるかどうかは、土地の用途地域や規制、建物の構造などに左右されます。
事前に不動産会社や税理士と相談し、最適な活用方法を検討するのが大切です。
親の老後資金や定期収入の確保
土地活用によって得られる家賃収入や駐車場収入は、定年後の生活費や医療費の補填に役立つでしょう。
特に、長期にわたって安定した収入を得られる形態であれば、年金だけでは不十分な場合のサポートにもなります。
親が健在なうちに土地活用の方針を話し合い、資金計画をきちんと立てておくことが重要です。
賃貸経営や太陽光発電といった方法は初期投資がある程度必要なので、金融機関の融資制度や補助金の活用も検討するとよいでしょう。
老後の暮らしを安定させるための手段として、実家の土地を最大限に有効活用することは大きな意義があります。
早めに動き始めることで、より効果的な収益を見込むことができるのです。
空き家・空き地の有効活用で地域トラブルを回避
空き家や空き地を放置すると、不法投棄や不法侵入が起こりやすくなるだけでなく、雑草の繁茂や害虫被害など地域全体へ悪影響を及ぼす可能性があります。
こうした状況は近隣住民とのトラブルを招きやすい要因となります。
一方で、実家の土地を賃貸物件や施設として活用すれば、管理が行き届き、周辺環境の維持にも貢献できます。
定期的な管理・巡回が行われる場所は、防犯面でもメリットがあり、地域の安心感につながります。
地域コミュニティとの関係性を良好に保てるかどうかは、長期的な土地活用の成功にも大きく影響します。
適切な活用方法や管理方法を選ぶことで、土地所有者と地域社会の両者にとってプラスになる結果が期待できるでしょう。
緑ボタンからタウンライフで
土地活用プランを一括比較!

POINT

あなたにぴったりの土地活用プランを無料で手に入れよう!

全国130社以上の優良企業に一括で依頼が可能!

依頼はオンラインでかんたん3分!
無料一括比較してみる
実家の土地活用方法一覧

土地や建物の特徴、周辺環境に合わせたさまざまな活用方法が考えられます。
実家の土地活用には、アパートやマンション経営のように賃貸収入を狙う方法のほか、駐車場・トランクルーム・資材置き場など、比較的投資額の少ない選択肢もあります。
どの方法を選ぶかは、立地条件やターゲット層、市場ニーズを把握したうえで検討する必要があります。
また、太陽光発電や高齢者向け施設などは、国や自治体の補助金制度が用意されていることも多いため、初期投資を抑えることができる可能性があります。
これらの制度を活用することで、リスクを最小限にしながら収益を生み出すことが期待できるでしょう。
実家の土地に適した活用策は一つとは限りません。
物件の状態や家族の意向とも照らし合わせながら、複数の選択肢を比較検討することが、最終的に満足のいく土地活用につながります。
※各項目をクリックすると詳細にジャンプします。
- アパート・マンション経営
- 戸建て賃貸経営
- 賃貸併用住宅の経営
- 駐車場・コインパーキング経営
- トランクルーム・倉庫経営
- 太陽光発電・ソーラー事業
- 資材置き場として貸し出す
- 高齢者向け施設・介護施設に活用
- 貸し店舗やテナントオフィス経営
- 借地として活用する
- 民泊・宿泊施設やキャンプ場への転用
アパート・マンション経営
集合住宅を建設し、多くの入居者から家賃収入を得る王道の土地活用法です。
周辺に大学や企業が多い都市部では、安定的な需要が見込めるでしょう。
ただし、大規模投資となるため銀行融資利用や事業計画の入念な作成が欠かせません。
建築費用や維持管理費、空室リスクなどに対するリスクヘッジをしっかり行うことが大切です。
将来的に資産価値が残る点や、節税効果が期待できる点がメリットですが、立地や管理運営次第では収益が変動することも忘れてはいけません。
戸建て賃貸経営
一戸建てを建てて貸し出す利点として、ファミリー層や在宅勤務者など、広い住空間を求めるニーズを取り込みやすい点が挙げられます。
庭付き物件は子育て世帯にも人気があり、長期入居が期待できる可能性があります。
建物規模が比較的コンパクトで済むため、アパート建設よりも投資金額を抑えられる場合が多いです。
ただし、一棟につき入居者は1組なので、空室になると家賃収入がゼロになるリスクもあります。
土地の広さや形状、周辺施設との距離などを踏まえ、自分の実家の特性に合った設計を行うことで、より高い需要を狙うことができます。
賃貸併用住宅の経営
自宅と賃貸区画を同じ建物内に設けることで、家賃収入と自身の住居スペースを両立させる方法です。
住宅ローンの返済を家賃収入で補えるため、金銭的負担を緩和できるメリットがあります。
実際に利用する居住スペースがあるので、建物や敷地の管理もしやすく、空き家リスクを大幅に抑えられるでしょう。
一方、入居者との生活スペースの近さが気になる人にとっては気疲れも懸念材料になります。
立地条件や設計プラン次第では魅力的な住居兼賃貸物件となり、広い世代をターゲットに安定的な収益を得られる可能性があります。
駐車場・コインパーキング経営
更地にして舗装し、月極駐車場やコインパーキングとして運用する方法です。
他の建築物を建てるケースと比べて初期投資が少なく、運営コストも抑えやすいのが特徴です。
交通量が多く、車を利用する人が多い地域であれば、比較的安定した収益を確保しやすいでしょう。
ただし、競合する駐車場が多いエリアでは料金設定などで差別化を図る必要があります。
また、土地を将来的に別の用途に転用したい場合でも、駐車場は建物ほど撤去やリフォームに手間がかからず、柔軟な対応が可能です。
トランクルーム・倉庫経営
近年、物を収納したい個人や事業者向けのトランクルーム需要が高まっています。
空き地にコンテナを並べたり、空き家内部に収納スペースを設けたりといった形で、比較的手軽に始められる事業です。
月々の利用料が収入源となり、利用者が増えれば安定したキャッシュフローを見込むことができます。
ただし、湿気や温度管理を必要とするトランクルームの場合は、設備投資が多めになる点に注意が必要です。
空間を有効活用できれば、都市部や住宅密集地だけでなく、郊外でも一定のニーズが期待できます。
自宅からの管理が可能であれば、維持コストを抑えながら運営することも可能です。
太陽光発電・ソーラー事業
広い屋根や土地がある場合、太陽光パネルを設置して売電収益を得ることができます。
近年は再生可能エネルギーへの注目が集まっており、国や自治体による補助金制度も活用できるケースが多いです。
設置場所や日照時間に左右されますが、安定した発電量が確保できれば長期的に利益を得られます。
ただし、パネルの清掃や定期メンテナンスが必要になるため、管理コストもしっかり見込んでおく必要があります。
電力の買い取り価格が変動するリスクはあるものの、土地や屋根スペースを大きく活用したい人にとっては有望な選択肢の一つです。
資材置き場として貸し出す
建築関連企業や運送会社などに、空き土地を資材や車両の保管場所として貸し出す方法です。
初期費用が比較的少なく済み、賃貸借契約を結ぶだけで安定した収入が得られる可能性があります。
ただし、騒音や粉塵などの問題が発生する恐れがあり、周辺住民からの苦情につながることもあります。
事前に利用ルールを明確に設定し、近隣とのトラブルを防ぐ配慮が必要です。
立地にも左右されますが、駅や主要道路から遠い土地でも需要が見込めることが多く、通常の住宅用地としては活用が難しいケースでも有効な手段となることがあります。
高齢者向け施設・介護施設に活用
高齢化社会の流れを受けて、介護施設やサービス付き高齢者向け住宅の需要は増加傾向にあります。
これらの施設を運営するためには一定の法的要件や運営母体が必要ですが、地元の福祉ニーズに応える形で長期的な安定収入を得られる可能性があります。
建設時や人員配置にコストがかかるため、ハードルは高めですが、行政機関や医療法人との連携、および補助金制度の利用で初期の負担を軽減できるケースもあります。
高齢者向け施設として地域社会に貢献できる点は大きな魅力です。
一方で、法令や衛生管理などの規制が多岐にわたるため、専門家のサポートを受けて確実に準備を進めることが求められます。
貸し店舗やテナントオフィス経営
商業施設やオフィスビルとして土地を活用することで、テナントからの安定した家賃収入を見込むことが可能です。
駅や商業エリアに近い立地であれば、集客力も高くなり、需要が途切れにくいというメリットがあります。
ただし、建設費用が高額になりやすく、建築や内装デザインにこだわるだけでなく、ターゲットとなるビジネスや顧客層を分析する必要があります。
テナントの離退去がある場合のリスクも考慮しておくと良いでしょう。
地域経済の活性化に貢献する側面もあり、うまく軌道に乗せられれば長期的な収益源を確保できます。
将来的に住居や別の用途に転用する計画も視野に入れておくと、リスク分散が図れます。
借地として活用する
借地契約を結んで土地を他者に貸し出すことで、建物を所有するリスクを負わずに賃料収入を得る方法です。
地主としての責任はあるものの、建築や運営にかかわるコストやリスクは借主側が負担することになります。
契約条件によっては、借地借家法などの法制度が絡むため、長期的な視点での収益構造を計算しておくことが大切です。
借地の契約期間や更新条件をしっかりと詰めておかなければ、後のリスクになる場合もあります。
シンプルに土地だけを貸す形態なので、比較的管理の手間が少ないのはメリットです。
ただし、借主が見つからなければ収入が途絶えてしまう恐れがあるため、市場調査や契約先の選定が重要になります。
民泊・宿泊施設やキャンプ場への転用
近年は観光地や自然豊かな地域での滞在ニーズが高まっており、ゲストハウスやキャンプ場などに転用する選択肢も注目を集めています。
既存の住宅をリフォームして民泊用に整備すれば、比較的低コストで始められることもあります。
ただし、住宅宿泊事業法などの法規制をクリアし、消防設備や衛生管理を整える必要があるため、事前の準備は欠かせません。
オペレーション面でのノウハウやゲスト対応の手間も考慮に入れるべきです。
アウトドアブームに乗じてキャンプ場として活用する場合は、景観作りや防災対策に注意を払いつつ、シーズナルな需要を狙うことで効率的に収益を上げられる可能性があります。
緑ボタンからタウンライフで
土地活用プランを一括比較!

POINT

あなたにぴったりの土地活用プランを無料で手に入れよう!

全国130社以上の優良企業に一括で依頼が可能!

依頼はオンラインでかんたん3分!
無料一括比較してみる
実家の土地を売却・寄付・相続放棄する選択肢

活用するだけでなく、売却や寄付、相続放棄という選択肢も状況によっては有力な手段となります。
土地活用と比較して一度にまとまった資金を得られる売却は、大きなメリットがあります。
しかし、将来的な地価上昇や長期的な賃貸収入といった利益の可能性を手放すことにもなるため、慎重な検討が必要でしょう。
寄付や相続放棄、国庫帰属制度などは、管理コストや負担の重さを回避したい場合に検討する選択肢です。
ただし、手続きや受け入れ要件が厳しく、思うように受理されないケースも考えられます。
自分や家族で土地を活用する意義が薄い場合や、遠方で管理が難しい場合など、それぞれの状況によっては手放すことがベターな選択肢となることがあります。
※各項目をクリックすると詳細にジャンプします。
売却のメリット・デメリット
売却の大きなメリットは、一度にまとまった現金を手に入れられる点です。
相続に伴う費用を一気に整理したい、投資資金を確保したいなど、資金面での柔軟度が高まります。
一方で、将来的に地価や需要が高まる可能性がある地域でも手放してしまうため、後から機会損失を感じるリスクもあります。
賃貸経営などによる継続的な収入も期待できなくなる点もデメリットです。
地域の不動産市況や税金面も考慮し、専門家に査定を依頼することが重要です。
売り急ぐと相場より大幅に安い価格で売却してしまう危険もあるため、計画性を持った売買戦略を立てましょう。
寄付や相続放棄・国庫帰属制度の特徴
寄付や相続放棄は、土地の管理や税金の負担を避ける手段として検討されることがあります。
特に相続放棄は、相続開始後に一定期間内でしか手続きができない点に注意が必要です。
最近登場した国庫帰属制度では、一定の要件を満たせば国が土地を引き取りますが、引き取り条件が多岐にわたり対象外となるケースも少なくありません。
事前の調査と手続きの正確さが求められます。
これらの手段は土地に対する責任を大きく軽減できる一方、一度手放した資産は将来的に取り戻すことがほぼ不可能です。
最終的な決断をする前に、税理士や弁護士などへの相談をおすすめします。
緑ボタンからタウンライフで
土地活用プランを一括比較!

POINT

あなたにぴったりの土地活用プランを無料で手に入れよう!

全国130社以上の優良企業に一括で依頼が可能!

依頼はオンラインでかんたん3分!
無料一括比較してみる
実家の土地を活用する前に確認すべきポイント

土地を有効活用し始める前に押さえておくべき基礎的な条件や準備を整理しましょう。
相続登記が済んでいるか、共有者がいないかといった名義・権利関係の確認は、活用の第一歩です。
こうした確認を怠ると後にトラブルが生じ、せっかくの計画を頓挫させてしまう可能性があります。
また、地域の都市計画や用途地域を把握しておくことで、建築可能な構造や事業内容の制限を事前に知ることができます。
思わぬ規制で計画変更を余儀なくされるリスクを減らすためにも、自治体の窓口や専門家に相談しておきましょう。
不要になった建物の解体費用や親族との協議など、事前準備が大変な側面もあります。
しかし、これらのポイントを確実に押さえることで、スムーズな土地活用へとつなげることが可能になります。
※各項目をクリックすると詳細にジャンプします。
土地の名義や権利関係
相続登記が未了の状態では、法的にその土地を自由に活用したり処分したりすることが難しくなります。
相続人が複数いる場合は共有状態となり、賃貸経営などを始めるには全員の同意が必要です。
名義人が変更になる手続きは煩雑ですが、早めに終わらせておくほど後の計画がスムーズに進みます。
特に賃貸ニーズの高まりが見込まれる時期を逃してしまうと、収益の機会損失につながるでしょう。
権利関係を明確にしておくことで、金融機関からの融資や専門家への相談も的確に行えるため、土地活用の成功確率が大きく高まります。
法的規制や都市計画
土地をどのように使えるかは、都市計画法や建築基準法などの規制で大きく制限されます。
例えば、住居専用地域では大規模な商業施設を建てられないなど、用途地域によって建てられる建物の種類や規模が変わります。
防火地域や準防火地域に指定されているかどうかもチェックが必要です。
建物の耐火性能や構造に影響するので、建築費用に直結するケースもあります。
こうした法的規制を無視して計画を進めると、着工後に発覚してやり直しを迫られるなど手痛い失敗につながるため、必ず事前に調査を行いましょう。
解体が必要なケースと費用
実家の建物が老朽化している場合、活用前に解体が必要になることが少なくありません。
解体工事には数十万円から数百万円の費用がかかるケースもあり、予算のうちに入れておくべき項目です。
解体業者によって見積価格が大きく異なることもあるため、複数社から相見積もりを取得するのが一般的。
さらに、アスベストをはじめとした有害物質の処理が必要な場合は追加費用が発生します。
解体タイミングや撤去後の地盤調査も含め、総合的にスケジュールを組むことで効率よく次の土地活用ステップに進むことができます。
親族との話し合いとトラブル回避
相続で複数人が関わる場合、土地活用の方針を決める際に意見の食い違いが生じることがあります。
特に、利益配分やリスク負担の考え方が一致しないと、後から大きな問題に発展しやすいです。
事前に親族全員が集まって話し合い、土地活用のメリット・デメリットを共有することが大切です。
専門家を交えて議論することで、客観的な視点を取り入れながら合意形成を図ることができます。
合意内容を文書化しておくことも有効な手立てです。
将来の紛争を防ぐためにも、早めの段階でクリアな意思統一をしておきましょう。
実家の土地活用の進め方・ステップ

土地活用を実際に進めるうえでの大まかな流れと、押さえておきたいポイントを解説します。
まずは専門家への相談や市場調査を行い、土地の特性や建物の状態、ニーズを把握するステップが重要です。
そのうえで事業計画を作り、資金調達や家族間の合意を得てから実際の建設や運営に移行します。
各段階で必要となる書類や手続き、費用が異なるため、あらかじめフローを可視化しておくことが成功のカギです。
急いで進めても思わぬ落とし穴にハマることがあるため、余裕をもって計画を立てましょう。
完成後は管理・運営が長期にわたり続くため、信頼できる管理会社や地域のサポート体制を確立しておくと安心です。
※各項目をクリックすると詳細にジャンプします。
専門家や不動産会社への相談
税理士に税務面の優遇制度や相続税の計算について助言を求め、弁護士には相続人間のトラブルを回避するための法的手続きを確認します。
不動産会社は、周辺の家賃相場や市場動向に関する有益な情報を提供してくれるでしょう。
専門家に相談することで、最適な土地活用プランを検討しやすくなり、無理のない投資や賃貸経営を実現しやすくなります。
特に建築会社との打ち合わせは、費用や工期の把握をするうえで重要です。
多角的なアドバイスを得ることで、リスクを最小化しながら、実現可能な形での土地活用が期待できます。
市場調査と需要ニーズの把握
どのような用途に需要があるかを知るためには、周辺地域の人口動向、経済状況、賃貸需給バランスなどを調べる必要があります。
インターネットの情報だけでなく、実際に現地を歩き回って雰囲気をつかむことも大切です。
競合他社の賃貸物件数や空室率を調査することで、自分の土地に適した賃貸料や設備内容を設定しやすくなります。
市場調査が不十分だと、想定した収益を得られない可能性が高まります。
地域住民のニーズを細かくリサーチし、それに合わせた施設や建物を企画できれば、空き室やテナント退去のリスクを大幅に減らすことができるでしょう。
事業計画書の作成・資金調達
具体的な収支シュミレーションとリスク対策を盛り込んだ事業計画書があると、銀行融資の審査が通りやすくなるだけでなく、実際の賃貸経営のロードマップとしても役立ちます。
初期投資にかかる建築費や解体費、運営にかかわる管理費や広告費など、可能な限り細かく試算しておくことが大切です。
補助金や助成金が利用できる活用方法であれば、そちらも併せて検討するのが良いでしょう。
計画書をベースに、投資家や金融機関との交渉を進めることで、より有利な条件で資金を調達できる可能性が高まります。
工事・施工と完成後の管理方法
施工会社との契約を結んだら、着工から完成までのスケジュールを明確にし、定期的な進捗確認を行います。
工事中に問題が発生した場合は、迅速に対処して予定の遅延を最小限に抑えることが重要です。
完成後の管理や運営では、入居者募集や賃貸契約、修繕対応など多岐にわたる業務が発生します。
自主管理が困難な場合は、不動産管理会社に委託することで負担を軽減できます。
長期的な収益を確保するためには、定期的なメンテナンスや入居者とのコミュニケーションが欠かせません。
アフターサービスやリフォーム計画も含め、継続的な運用体制を整えておきましょう。
自分に合った土地活用方法を探すには一括サイトの利用がおすすめ
自分に合った活用方法を探すには、複数の専門家に見積もりを依頼することが高価的です。
そうすることで、自分の土地の市場価値や選択肢の幅が広がり、自分では気づかなかった活用も可能になります。
でも、一社一社に見積もりを依頼するのも大変ですよね?
そこでおすすめなのが「一括比較サイト」です。
あなたの希望条件に合わせた土地活用方法を一括で複数社に依頼できますので、時間を短縮しつつ最適な業者を見つけることができます。
おすすめは「タウンライフ土地活用」!

一括比較サイトで最もおすすめするのがタウンライフ土地活用 というサイトです。
なぜおすすめなのかというと、
全国130社以上の優良企業が登録されており、『収益性』・『費用』・『転用性』・『相続時の評価額』・『実現性』など多角的な視点からあなたに最適な空き家活用プランの提案を無料で行ってくれるからです。
とりあえず、まずは3分入力でタウンライフ土地活用 を使ってみてください。
緑ボタンからタウンライフで
土地活用プランを一括比較!

POINT

あなたにぴったりの土地活用プランを無料で手に入れよう!

全国130社以上の優良企業に一括で依頼が可能!

依頼はオンラインでかんたん3分!
無料一括比較してみる
まとめ・総括
実家の土地の活用にはさまざまな方法があり、しっかりと計画を立てれば大きなメリットを得られます。
税金や法規制を踏まえつつ、トラブルを防ぎながら手続きや施工を進めていきましょう。
実家の土地を放置すると、税負担や老朽化、近隣トラブルなど多くのリスクが生じるため、早期の活用が推奨されます。
アパート・マンション経営や駐車場、資材置き場など選択肢は豊富で、それぞれに特徴やリスク・リターンがあります。
また、相続や税金の知識をきちんと身につけておくことで、節税効果を最大限に活かすことができ、長期的な経済メリットにつなげられます。
家族や専門家との連携を強化しながら、適切な判断と段取りを踏むことが重要です。
最終的には、自分や家族の価値観・将来計画を踏まえた柔軟な戦略が成功のカギとなります。
一歩ずつ確実に進めることで、大切な実家の土地を有益に活かせるよう取り組んでみてください。